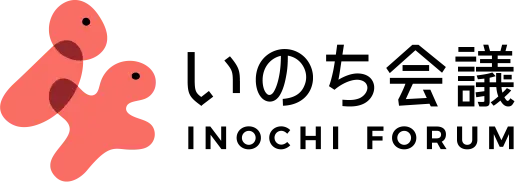アクションパネル
【開催報告】2024年8月8日(木)、いのち会議 アクションパネル 食・農業「食と農における科学技術の役割」を開催しました!

2024年8月8日(木)、いのち会議 アクションパネル 食・農業「食と農における科学技術の役割」を開催しました。話題提供者の方々含め会場に15名、オンラインで20名が参加しました。以下に概要を報告します。
岡野 嘉市(浜田化学株式会社代表取締役)「廃食油リサイクルによる持続可能な社会の実現」
✓ 浜田化学「人と循環で世界を救う」:55年前に天ぷら油のリサイクルでスタート、廃食油のリサイクル(全国でシェア7.6%)で持続可能な社会の実現へ貢献
✓ リサイクルフロー:回収した廃食油の99.7%をリサイクル、認定基準をクリアした油脂から飼料の原料にもリサイクル(持続可能な食のサプライチェーンに貢献)
✓ バイオディーゼル燃料(BDF):環境にやさしいイベントに活用(ルミナリエなど)
✓ カネカ生分解性バイオポリマー:自然に還る生分解性(海洋分解・土壌分解)
✓ 廃校を利用した循環型農業(淡路島):環境負荷の低い栽培(白いちご淡雪)
✓ 飲食事業:自然派素材にこだわったタイ料理など。学びの場にもしていきたい
✓ EXPOグリーンチャンレンジ、CSR活動など;食の循環に関する啓蒙
⇒ 一緒に「ムダナクオイシク」を進めていきませんかという提案
花井 淳一(グリーン株式会社 取締役CPO)「農業IoTやAIを活用した国内外でのスマート農業の実践
✓ 2024年4月創業:元ソフトバンクの農業AI開発・運営担当からスピンアウト
✓ ビジョン:情報活用で一次産業の新たな価値創造、環境・資源・食料問題解決へ
✓ e-kakashi:データによる栽培アシスト→収益向上、技術伝承、環境に優しい農業
*環境情報の定期計測・機械学習による勘や経験だけに頼らない農業へ
✓ 計測データの使い方:見える化だけで十分か?役に立つのか?
→科学的根拠と栽培ノウハウの融合による観測だけでなくナビゲート機能の搭載
✓ データ収集に加えて、分析結果・対応策共有のためのWS実施:若手とベテランの交流促進、ナビゲートにも反映→根本課題である後継者育成に貢献
✓ 経済・経営面での支援も:持続可能な農業に必要な部分
✓ 海外展開:11ヶ国で展開。病気発生予測・収穫適期予測など
✓ 持続可能な農業へ:メタン発生抑制・水資源の最適利用、CO2吸収量の推定・見える化システムなどを通じて環境にやさしい農業・脱炭素化社会の推進
⇒ データ主導型農業(品質・収量向上、管理・栽培コストの低減だけでなく、バイオマス最大化・CO2固定化などで環境負荷の低減へ)でサーキュラーエコノミー実現へ
岸 大介(株式会社LIFULL Agri Loop代表取締役)富士榮尚寛(伊藤忠テクノソリューションズ株式会社みらい研究所長)「肥料化触媒技術Poop Loopによる循環型社会の実現」
✓ 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC):循環型社会の実現、微生物・土壌への着目するなかで、Agri Loopと事業提携し、IT面での事業支援(Poop Loop)
→悪臭除去、汚染対策、持続性向上(自動化)などの可視化・分析
✓ Agri Loop:肥料化触媒技術PoopLoopによる循環型社会の実現(←栄養素低下)
✓ 土壌劣化:不自然な営みとしての農業→「土に栄養を戻す」メンテナンスが必要
→滞留した有機廃棄物を土に戻すことで物質循環の適正化を図る
✓ 家畜排泄物:現状輸入化学肥料で補っている分の窒素を家畜排泄物でまかなえる
→鉄触媒を利用し、堆肥より効率的(20~45%→約75%)に窒素を土に戻す
*堆肥そのままだと発生する悪臭・温室効果ガスが発生するのを防ぐ効果も
✓ 糞尿の適性処理による蓄産・栽培の効率・安定化効果+硝酸流亡(公害)防止
*石垣島珊瑚礁:海洋多様性の要、牛糞・肥料からの窒素流出低減による保護効果
⇒ 鉄触媒による肥料化によって窒素循環適正化による土壌を健康化、栄養素豊富な農作物生産、現在流出している硝酸減少による公害防止・環境保護へ
田畑 彩生 (大阪大学薬学研究科MA-T酸化制御学講座 特任助教)「循環型酪農の実現に向けたMA-Tの可能性」
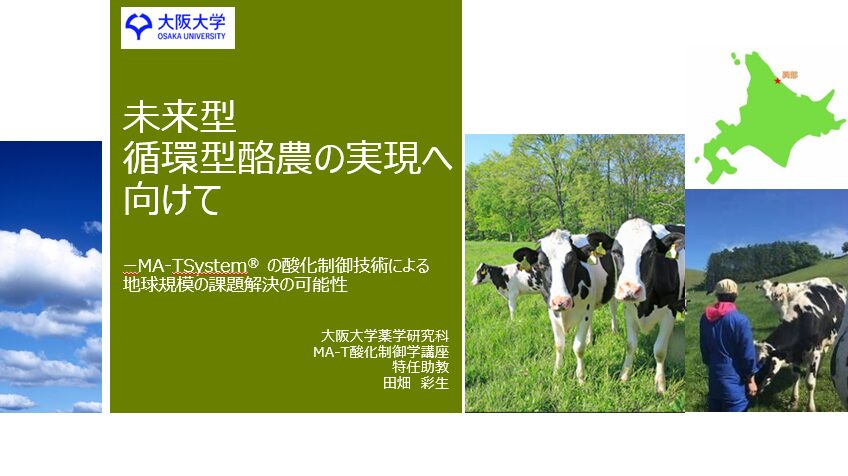
✓ MA-T System:酸化制御技術。医療・農業・エネルギーまで広く応用される技術
*常温常圧でメタノール合成をする大久保酸化ドリーム反応の実現
✓ COPの動き:CO2輩出削減(COP3)→メタンガス排出削減へ(COP26・27)
✓ メタンガス:日本は97.7%を輸入に頼る→発電、都市ガス、燃料に利用
→輸送の際にメタンガスの冷却(-162度)のために電気を使用→メタン酸化技術でCO2削減に繋がる
✓ 天然ガスのメタンを燃焼させずに液体燃料のメタノールへ常温常圧で返還する技術:エネルギー効率が50%→90%へ上昇
✓ 北海道興部町での実証実験:バイオガスプラントの稼働(←牛畜産の町)
✓ ドリーム反応の経済効果:輸入に頼るメタノール、ギ酸(全量輸入)を製造
→ 燃料・エネルギーの国内での生産、農業効率の改善など循環型酪農モデルへ
ディスカッション:モデレーション(田和)
今抱えている課題は?
岡野:グランドデザインを話し合う場がないまま国での議論が始まってしまう。きちんとデータを持ち寄って(情報技術の専門化にも入ってもらって)議論する場が出来てくれば
花井:日本以上に海外がそうだが、ただ「儲けたい」のではなく「楽して儲けたい」という気持ちがある。次世代継承について考える上でも、そこそこ頑張れば上手くいくようにすることも重要ではないか。最先端の追求だけでなく、人をおいつめないそこそこを目指す科学技術のあり方も。
富士榮:「楽する」ためにいかに使ってもらうか。「使っているという意識」がなくても「使えている」という状態にもっていけるか。同時に「楽する」ではなく「ズルする(データで嘘をつく)」という状況に陥らないように気をつける必要がある。きちんとエビデンス・データに基づいた状況改善が「楽する」ためには重要
岸:ハードルが高いのは農家の人に信じてもらうこと。農家の人のルーティーンをどう変えてもらえるか。少しずつ導入が進み仲間が少しずつ増えていけば、「サイエンス」として変えていく事ができるか
田畑→井上:Agri Loopと連携できれば(窒素のAgri Loop、炭素のMA-T)より大きな事が出来るのではないかと感じた。是非大阪大学にお声がけいただければ
会場・オンライン質問
Agri Loopのモデルはどれくらいの規模なら適用可能なのか教えてほしい。
→岸:北海道では240頭、70ヘクタールで実施している。本州では200頭・20ヘクタールでまかなえるようにしたいと計画している(一部をトウモロコシなど高カロリー作物で補うなども検討中)