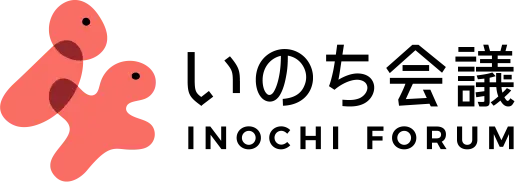活動状況|いのち宣言
【提言】芸術作品が時代を超えて奏でる「いのちの声」にみんなが耳をそばだて、いのちの理解を深める場を構築しよう
概要
現代は「いのちとは」という問いが大きな意味を持つ時代です。例えば、技術や医療の発展を考える時に対面する「いのちとは」という問いや、人工知能と人間について考える時の「いのちとは」という問いなどです。そして、様々な分野でこの問いへの答えを見つけるために試行錯誤が行われています。
目に見えない、形のない「いのち」とは何かを知る方法の一つが「ミュージアムで耳をそばだてる」ことではないでしょうか。なぜなら、ミュージアムにはいのちの声や思いが形になったものが大切に展示されているからです。今回は世の中にあるたくさんのミュージアムの中から「美術館」を例に話を進めます。
「美術館で耳をそばだてる」とはどういうことでしょうか。そこに展示されている作品について調査・研究をするということです。 美術館に展示されている作品は、「いのち」の声が、思いが、色になり形になり時には音になり言葉になり、私たちの目の前に登場したものだと思います。そうであるならば、それらを調査・研究することで「いのち」が浮かび上がってくるはずです。
古くは数万年前の洞窟に描かれた絵画から、今この瞬間に創造される作品まで、まさに、いのちによって様々な作品が生み出されました。でも、数万年前に洞窟で絵を描いた人はもう生きていません。だから、「その作品を生み出すいのちの声」を直接聞くことはできませんが、あきらめる必要はありません。なぜなら、現在私たちが目にするその洞窟の絵画は、数万年前の、その絵画が描かれた時代そのものなのです。それならば、私たちが適切にその作品を調査・研究し理解することができれば、その作品は当時のことを私たちに雄弁に物語ってくれるはずです。まさに時代の生き証人のように。
だから、私たちはその作品の声を正しく聞くために、正確に調査・研究しなければなりません。これが「耳をそばだてる」ということです。
でも、作品のことを調査・研究するだけでは「いのちの声」を聞くのに十分ではないと考えます。なぜなら、いのちはいのちだけで存在するのではなく、環境(自然、社会、制度など)の影響を多少の差はあっても受けているからです。なので、私たちは環境要因を考慮して「いのちの声」に向き合うことが重要になります。
例えば、大原美術館ではアーティストに滞在制作の機会を提供しています。その制作場所は100年前に画家が使っていたアトリエです。アーティストはただそこで製作するだけでなく、その土地を知るために、様々な場所に出かけたり、土地の人と交流をしたり、書物などを調べたりします。そうやって制作された作品は、時間(この時)と場所(この場所)と人(そのアーティスト)のどれが欠けても成立しなかったはずです。もし将来、この時代もしくはこの土地もしくはそのアーティストを知りたいという人が出てきたら、今創り出された作品はきっとその人に雄弁に「今、この時」を伝えるでしょう。そのために、記録を残し、作品を残し、将来世代が「耳をそばだて」た時にきちんと声が聞こえるようにしています。
「いのちとは」という問いが大きな意味をもつ現代、いのち会議は、大原芸術研究所などとのつながりを深めながら、多くの人がミュージアムを訪れ、芸術・作品自体および周辺情報から得られる様々な知見に触れ、「いのちの声」に耳をそばだてられる、そのような場を構築していきたいと思います。
参考情報
・コート―ルド 美術研究所
https://courtauld.ac.uk/about-us/
・アート インスティチュート オブ シカゴ
https://www.artic.edu/about-us
・大原芸術研究所
https://ohara-art-foundation.jp/service_category/service_category1/
関連するアクションパネルのテーマ
11. アート・文化・スポーツ
関連する「いのち」
いのちを「しる」
関連するSDGs