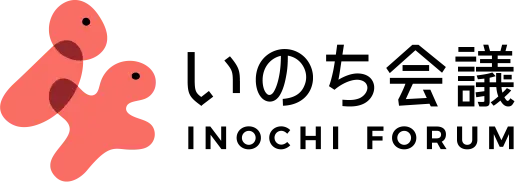いのち宣言アクションプラン
知的障がいのある人と友になり、すべての人が本当の自分でいることができる世界をつくろう
知的障がいのある人には特別な賜物があります。
知的障がいのある人は効率的ではありません。できることが制限されている場合が多いからです。重度の障がいのある人は食事介助など、たくさんの助けを必要としています。自ら行動することができないこともあり、存在そのものが他の人びととは異なった形で生活しています。
効率的で、有能になること、強くなることに価値を置く社会で、知的障がいのある人は、弱さにとどまるように生きています。弱さを生きることは辛いことでもあります。助けを得られないとき、周りと比較してしまうとき、友達がいなくさみしいときなど、生きづらく、苦しみは怒りや叫びとなって表現されます。
ラルシュかなの家のアシスタント(支援員)は生きづらさを抱えた知的障がいのある人を助けるためにかなの家にやって来ます。最初は障がいのある人を助けるために働きますが、アシスタントとして一緒に食事、仕事、アート活動、祈り、お祝いをする生活をしていくと、しだいに表面的な関係ではいられなくなります。喜びもぶつかりあいもある、正直で対等な関係を作っていくように招かれていきます。
知的障がいのある人の多くは肩書や過去を気にしません。また、幼少期に受けた私たちの心の傷に不思議な方法で触れてくる洞察力のある人もいます。小さな幸せを喜ぶことのできる人もいます。まわりからバカにされ嫌われても、愛することを恐れない人もいます。障がいのある人を支援すると同時に、相互の関係を作っていくなかで、私たちは効率主義ではない新しい価値観を発見します。
ラルシュかなの家では、このようにアシスタントや一般の人が、知的障がいのある人と出会い、本当の自分自身を見つけていくように変わっていくプロセスを大切にしています。
もし、あなたが知的障がいのある人と一緒に過ごし、友となることができれば、それは本当のあなた自身でいることの助けとなります。弱さを隠さない正直なかかわりは、少しずつあなた自身が持つ弱さをゆるすように導いてくれるからです。自分の弱さを許す方法を知らない私たちにとって、ただ一緒にいてくれる存在が必要です。知的障がいのある人たちは、弱さを通して存在そのままでいいと私たちに教えてくれます。
現状では、重い障がいのある人が社会で生活できる福祉制度にまだ十分なっていませんが、いのち会議は、ラルシュかなの家のような、知的障がいのある人、ない人が作る小さなコミュニティを大切にし、そうしたコミュニティがたくさんできていく社会を提案します。

ラルシュかなの家での交流の様子
それぞれのコミュニティでは、知的障がいのある人とない人が生活を分かち合い、色々なお客さんを迎えます。一緒に食事をして、祈り、祭り、お祝いをします。地域の人たちが知的障がいのある人と出会い友達になっていきます。
インクルーシブな社会は本当の自分でいられることを助けます。なぜなら、知的障がいのある人から「あなたの存在そのままでいい」というメッセージを受け取ることができるからです。たくさんの「いのち」のつながりによって生きていることを、知的障がいのある人の存在からも知ることができます。障がいがあること、弱さがあることは負い目ではありません。弱さは「わたしにとってあなたの存在は大切です」と伝え合うことを可能にします。
いのち会議もまた、強くて弱い私たちの「いのち」を喜び祝う輪が、少しでも広がっていくことを願って活動していきます。
【参考情報】
・ラルシュかなの家
http://larchekananoie.blog.fc2.com/
・ラシュル・インターナショナル
【アクションパネル】
医療・福祉
【SDGs】