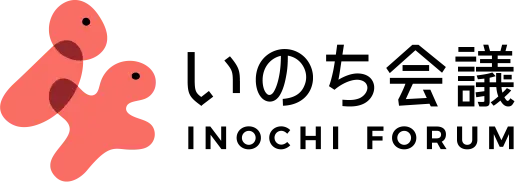いのち宣言アクションプラン
言葉にならない経験をしたとき、「自分だけ ? 」「どうせ誰もわかってくれない ! 」と孤独な気持ちになることがあるでしょう。そんなモヤモヤをもちよって、一緒に言葉をつくってみませんか
私たちは皆、異なる身体と環境を生きています。だから当然、互いの経験内容は異なります。また、身体や環境が多数派と大きく異なる人は、経験内容も多数派と大きく異なる可能性が高まるでしょう。世の中に流通している日常言語は、多数派の経験の中で繰り返されてきた共通項、いわば「あるあるエピソード」を結晶化したものなので、身体や環境の面で少数派の人々は「自分の経験を表す言葉がない」という状況に置かれやすく、自分の経験の解釈、未来の見通し、出来事の実在性、他者との共感的な経験の分かちあいといったことが難しくなって孤立しがちです。
日常言語では表せない経験も、専門用語なら表せるということもあります。専門用語に出会って、長年、意味づけできずにいた、もやもやした経験を「確かにあるもの」として捉えられるようになり、その経験とのつきあい方にも見通しを得られるようになったという少数派の人びとは少なくないでしょう。しかし、自らがその経験をしたわけでもない専門家が多数派を占める研究コミュニティが生み出す言葉や知識は、当事者の経験を十分に表現しきれていないこともまれではありません。日常言語がマジョリティのあるあるエピソードにカスタマイズされていることによる不公平な状況を、哲学者のミランダ・フリッカーは「解釈的不正義」と呼びました※1。
こうした不正義を是正すべく、日常言語でも、専門用語でも、十分に表しきれない経験を抱えた人びとが始めた研究活動が「当事者研究」であり、類似した経験をもつ仲間とともに、自分たちの経験を表す言葉やフレーズを生み出したり、経験の規則性に関する知識を生み出したりする活動を意味します※2。もともとは精神障がいや依存症、発達障がいの人々の間で始まったこの活動は、やがて、子育てのモヤモヤを言葉にしたいと感じるお母さんや、理由もわからず学校に通えないこどもたち、刑務所出所後の苦労に関して周囲に伝える言葉を探している元受刑者、名状しがたいストレスを抱えた企業人などにも広がり、属性や背景の違いを超えた研究コミュニティを構築しつつあります。

フィンランド、イギリス、韓国、日本の当事者が一堂に会して、通訳システムと手話、字幕を駆使して当事者研究を行っている様子
たとえば2001年以降、当事者研究は、精神病院に長期入院してきた人びとや、刑務所から出所した人びとの地域定着を支援する方法として活用されてきました※3。また2008年以降に活発化した自閉スペクトラムの当事者研究は、当事者から提案された仮説を科学的に検証することで、ボディイメージや声のコントロールの不安定さ、パーソナルスペースの狭さなど、新しい知見をもたらしました※4。さらに、当事者とともに開発したVR擬似体験と、当事者の語りを収録した動画の視聴を組み合わせたプログラムが、受講生の自閉スペクトラムに対する差別偏見を減らすことも見いだしてきました※5。最近では、企業や福祉施設などの組織を、多様な人びとが活躍できる場へと変革するための方法として、当事者研究が活用されはじめています※6。
孤立と分断が深まりつつある世界の水面下で進行している見えにくい格差の一つが、「解釈的不正義」なのではないでしょうか。東京大学先端科学技術研究センター当事者研究分野の熊谷晋一郎教授をはじめとした研究者のグループは、これまで、医療、福祉、教育、司法、街づくり、企業経営など、様々な領域でこの当事者研究を導入することの効果を観察してきました。近年では、日本で誕生した当事者研究に関心を持つ海外の研究者や市民も増えてきています。
いのち会議は、こうした研究者たちとともに、2050年に向けて、当事者研究が様々な領域に実装されることを目指します。
【註】
※1 佐藤邦政・神島裕子・榊原英輔・三木那由他(編著)『認識的不正義ハンドブック』(勁草書房、2024年)
※2 Tojisha-kenkyu
https://aeon.co/essays/japans-radical-alternative-to-psychiatric-diagnosis
※3 札幌刑務所における精神障害受刑者処遇・社会復帰支援モデル事業
https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei08_00128.html
※4 “How autism may stem from problems with prediction”
https://www.thetransmitter.org/spectrum/autism-may-stem-problems-prediction/?fspec=1
※5 東京大学先端科学技術研究センター「自閉スペクトラム症の知覚を体験することでネガティブな感情が改善される」
https://www.rcast.u-tokyo.ac.jp/ja/news/release/20230803.html
※6 当事者研究の導入が職場のウェルビーイングと創造性に与える影響に関する研究(UMIN000048418)
https://rctportal.mhlw.go.jp/detail/um?trial_id=UMIN000048418
【アクションパネル】
多様性・包摂
【SDGs】