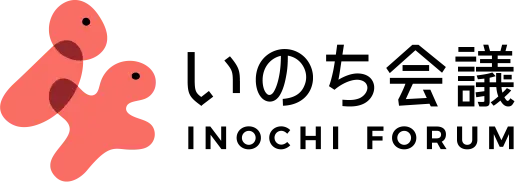いのち宣言アクションプラン
こどもや若者たちが自らのアイデアを分かち合える新たな仕組みを築き、互いに協力し、解決策に貢献することを通して、災害に立ち向かう力をはぐくみ、世界規模での防災力向上の一員となれるようにしよう
国連の「子どもの権利条約」では、こどもたちが健康的な環境で暮らし、自らの生活に関わる意思決定に参画する権利が保障されています。今日、こどもたちの生活に深く影響を及ぼす大きな問題のひとつが、気候変動に起因する災害の脅威です。「すべての人に健康と福祉を(Goal 3)」および「気候変動に具体的対策を(Goal 13)」は、持続可能な開発目標(SDGs)にも掲げられています。こうした複合的な課題に取り組む際には、こどもや若者たちとともに、彼ら自身によって、そして彼らのために取り組みを進める必要があります。これは、「いのち宣言」の「はぐくむ」、および「仙台防災枠組 2015–2030」※1と一致するアプローチです。
災害に関連する大きなリスクのひとつは、長期にわたるメンタルヘルスの問題で※2、特に、災害を複数回経験した人びとにとってその影響は顕著です※3。こうしたメンタルヘルスの問題は、災害そのものの体験だけでなく、住宅、学校、地域サービスの破壊や、それによって地域社会およびサポートの仕組みから離れて暮らさざるを得ないなど、その後の数年にわたる生活環境の変化からも生じます。また、気候変動への強い不安を抱えるこどもや若者たちにおいても、同様の問題が発生することがあります※4。
こどもや若者たちが防災に貢献してきた事例は数多くあります。たとえば、ニュージーランドのカンタベリー大学の学生たちが SNS を活用して立ち上げた「学生ボランティア団体(Student Volunteer Army)」は、クライストチャーチ地震後の支援活動で重要な役割を果たしました。防災教育や災害体験後の支援プログ ラム※5,6も、こどもや若者たちの参加を促す有効な手段です。しかし、就学前児童、障がいのあるこども、文化的・民族的背景の異なる持つこどもといった特別な支援を必要とするこどもたちのメンタルヘルスや幸福感を支援する最良の方法については、さらにエビデンスが求められています。
こどもや若者たちが、防災についての考えや意見を発信できる一貫した仕組みがあれば、彼らの声の重要性が広く理解され、意思決定の場にその経験が当たり前のように反映されるようになります。また、それによって世界中の若者たちが連携し、新しいアイデアを共有し、互いに学び合う機会が生まれます。
各国・各地域において、「若者による防災リーダーシップ・ネットワーク」を段階的に整備することは、政府系・非政府系の防災機関が果たすべき継続的責務であると言えます。こうしたリーダーシップグループやネットワークは、若者たちが地域防災に貢献できる力を高め、主体的な行動への自信と可能性を育む土台となります。また、就学前のこどもたちも、学校や地域などの支援環境を通じて、ネットワークの一員として参加することが可能です。あらゆる年齢、ジェンダー、能力、家族背景、生活環境を持つこどもや若者たちが、等しく関われる機会を保障すべきです。
この構想の実現には、他の若者やおとな、関連団体からの支援が必要です。支援者たちは、若者が災害関連のストレスに対応するスキルを身につけ、他者を安全かつトラウマに配慮した方法で支援できるよう協働します。また、若手リーダーの入れ替わりを前提とした継続的な活動体制も必要です。政府、医療、防災、教育機関のおとなたちは、こどもや若者から学ぶ姿勢をもち、彼らの意見が実際の変化につながるような「安心して発言できる場」を創出することが求められます。
こうしたグループの立ち上げには、特に災害後の混乱期においては困難が伴います。しかし、西オーストラリアの若者たちと研究者たちが蓄積してきた知見(https://shorturl.at/lyjKe)は、若者の防災参画を進めるうえで非常に有益です。災害が起こる前に備えておくことが鍵となります。神戸で2025年1月に開催された、阪神・淡路大震災30周年の追悼イベントのように、過去の災害を記憶し伝える活動は、次世代の学びと防災意識の醸成に役立ちます。
アメリカ合衆国の「FEMA ユース防災評議会(The Federal Emergency Management Agency, Youth Preparedness Council)」や、オーストラリアの「若者と災害に関する国家先端研究機関(The National Centre of Excellence: Young People and Disasters)」は、若者による防災リーダーシップを具現化する多様なモデルを示しています。
いのち会議は、既存の取り組みの成功事例を広め、国を越えたネットワークの形成を関連組織と協力して呼びかけることで、若者による防災・復興ネットワークの構築を推進します。それは、おとなたちがこどもと若者のニーズを理解し、主体的な参加の場を整えることにつながり、より有効な解決策を共に設計していく一歩となるでしょう。さらに、こうしたネットワークによって、こどもや若者たちが、「影響を与えられる範囲(自分でコントロールできる領域)」に意識を向け、つながりを通して、自分たちの未来を築いていくことが可能になるでしょう。
【註】
※1 仙 台 防 災 枠 組 2015–2030(The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030)https://recovery.preventionweb.net/ja/the-citizens-guide-to-the-sendai-framework-for-drr-japanese
※2 Newnham EA, Mergelsberg ELP, Chen Y, Kim Y, Gibbs L, Dzidic PL, et al. Long term mental health trajectories after disasters and pandemics: A multilingual systematic review of prevalence, risk and protective factors. Clinical Psychology Review. 2022;97: 102203. doi:10.1016/j.cpr.2022.102203.
※3 Leppold C, Gibbs L, Block K, Reifels L, Quinn P. Public health implications of multiple disaster exposures. The Lancet Public Health. 2022;7:e274-86. doi: 10.1016/ S2468-2667(21)00255-3
※4 Léger-Goodes T, Malboeuf-Hurtubise C, Mastine T,
Généreux M, Paradis PO, Camden C. Eco-anxiety in children: A scoping review of the mental health impacts of the awareness of climate change. Frontiers in Psychology. 2022;13:872544. doi: 10.3389/fpsyg.2022.
※5 Amri A, Haynes K, Bird DK, Ronan K. Bridging the divide between studies on disaster risk reduction education and child-centred disaster risk reduction: a critical review. Children’s Geographies. 2017;16(3):239-51. doi: 10.1080/14733285.2017.1358448
※6 Gibbs L, Marinkovic K, Nursey J, Tong LA, Tekin E, Ulubasoglu M, et al. Child and adolescent psychosocial support programs following natural disasters – a scoping review of emerging evidence. Current Psychiatry Reports. 2021;23(12):23(12):82. doi: 10.1007/ s11920-021-01293-1.
【アクションパネル】
医療・福祉
【SDGs】