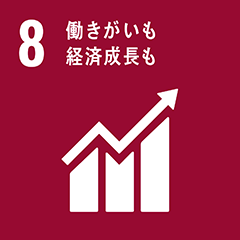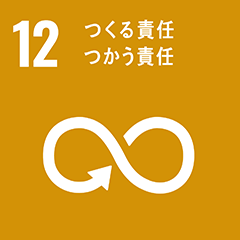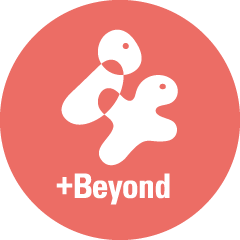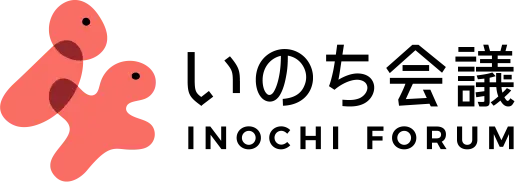いのち宣言アクションプラン
一人ひとりが勤労者・投資家・購買者として、企業の社会価値を表す ESG 情報で企業選択をすることにより社会に好循環を生むことで、「三方よし」の持続的社会経済を実現しよう
30年間、日本ではGDP がほとんど成長せず、労働生産性もまた低いままです。労働生産性とは、金銭的な価値、すなわち付加価値額を労働時間あたりどのくらいつくれるかを表します。労働者の人口が増えないなか、世界史でも極めて希なGDP 比240% の国家債務を抱え、今後の利払い増加も懸念されます。財政を立て直し、持続的な社会を支えるためには、労働生産性を向上させて付加価値額を確保することが必要です。日本は、商品・サービスの値付けの高さを示すマークアップが世界の標準とくらべてかなり低い状態です。また労働の値付けである実質賃金も、30年間ほぼ横ばいか減少傾向です。
この課題を解決するために、大阪大学社会ソリューションイニシアティブ(SSI)の基幹プロジェクト「ステークホルダー・ESG 経営とエシカル消費・サステナブル調達の促進による共感経済の実現」(代表:伊藤武志 社会ソリューションイニシアティブ(SSI)教授)では、売り手よし、買い手よし、世間よしの三方よしを目指し、企業や産業界が、買い手や世間の共感を得ながらマークアップを改善し、労働や商品・サービスにおける付加価値を高める道筋を探求しています。
具体的な道筋は、勤労者、投資家、購買者が、企業が開示する ESG(環境・社会・ガバナンス)情報によって比較評価した上で企業を選択できるようにし、その状況のもとで、企業が透明性をあげながら切磋琢磨することで、企業、業界、社会全体のESGレベルを向上させることです。ESG はサプライヤー、労働者、環境、地域などに対して企業がどう行動しているかを示します。言い換えれば、企業が社会に提供する価値、社会インパクトであり、それは企業ブランドを形作る実像です。企業の切磋琢磨による社会へのインパクトを向上させるために、本プロジェクトでは、ESG を比較するためのアプリ「サステナアプリ」を開発しています。このアプリは、環境、人権、社会貢献、アニマルウェルフェア、ガバナンスなどの項目ごとに企業努力をスコア化し、消費者や勤労者などが購買先や就職先を選ぶときの参考にしてもらうことを目指します。現在、ESG 開示の先頭に立つ株式公開企業だけでなく、非公開の企業にも参画をよびかけています。


サステナアプリのスクリーンショット
プロジェクトでは、ステークホルダーからの評価と応援をベースに、企業に対して「価値あるものに価格をつける」ことを提言しています。 ESG 向上にはコストがかかるものの、価値を伴ったESG のコストは本来、価格に転嫁されるべきものです。日本では、「失われた30年」を経ても、無償・過剰サービス、低賃金など、価値あるものに価格がつかない状況が続いています。特に急務なのは、ESG の「社会」に関わる賃金の引き上げ、すなわち労働の価値に適切な価格を付けることです。そのためには、すべての業界において、ESGという価値に適切な価格を付けて商品・サービスを売り切ることができな くてはなりません。そこで、企業だけでなく、購買者や投資家、勤労者をはじめとしたすべてのステークホルダーの共感と協力が必要となります。
今後、本プロジェクトでは、このようなビジョンに立って社会への働きかけを強めるとともに、AI を活用したデータ収集、ワークショップや体験会などの場づくり、いのち会議と連携する他の組織との協働、企業との共同研究を通してサステナアプリの開発と普及をさらに進めます。
いのち会議は、本プロジェクトとともに、勤労者、投資家、購買者がESG 情報を使って企業を選ぶための手法を開発し、ライフスタイルを確立することによって、企業が健全に付加価値を生み出す「三方よし」の好循環経済システムを皆でつくっていきます。
【参考資料】
・大阪大学社会ソリューションイニシアティブ(SSI)基幹プロジェクト「ステークホルダー・ESG 経営とエシカル消費・サステナブル調達の促進による共感経済の実現」
https://www.ssi.osaka-u.ac.jp/activity/core/empathyeconomy/
【アクションパネル】
経済・雇用・貧困
【SDGs】