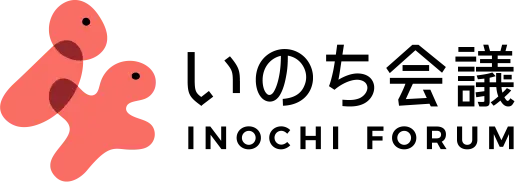いのち宣言アクションプラン
病や障がいのある人も含め、すべての人の中に健康というかけがえのない資産を育み、家族や地域、職場、そして地球のケアに、人びとが主体的に関わることのできる社会をともに築こう
大阪大学「グローバルヘルスと教育」ユネスコチェア(以下UO- UC)は、2018年に発足しました。その原点は、「すべてのこどもと若者が健康で充実した人生を送る機会を持つべきだ」という、シンプルで力強い理念にあります。
発足以来、UO-UC は、感染症や慢性疾患、性と生殖に関する健康、メンタルヘルス、社会的排除といった、子どもと若者が直面する多様な課題の理解と解決に取り組んできました。これらの課題は地球規模のものですが、解決の出発点は地域にあります─すなわち、学校、家庭、そして地域社会です。
UO-UC は、研究、協働、教育を通じて、公衆衛生、社会科学、そしてデザイン思考を橋渡しする独自のアプローチを構築してきました。その中心にあるのは、人びとが「何を必要としているか」だけで なく、「すでに何を持っているか」─すなわち、彼ら自身の強み、ネットワーク、創造力─に注目する姿勢です。この取り組みの核心には、「人と人の関係性を育むこと」「学びを支える環境を育むこと」「地域社会が自らと互いをケアする力を育むこと」が据えられています。

UO-UC の教育プログラムで活動する学生達
UO-UC の活動は、SDGs ─特に目標3(健康)、目標4(教育)、目標5(ジェンダー平等)─と深く関わっています。しかし、 SDGs の期限が近づく今、私たちは次の問いを立てる必要があります。それは「私たちは何を学び、そしてこれからどこへ向かうのか」という問いです。
UO-UC の視点から、以下の3つの教訓が明確になっています:
1.健康システムは「課題」ではなく「強み」から出発すべきです。 UO-UC は、「ヘルス・アセット(人びとやコミュニティが健康を維持・向上するために活用できるあらゆる資源)」アプローチを重視して おり、地域社会がすでに築いている相互扶助の文化─関係性、共有された空間、地域の知識─に価値を見出しています。
2.実際の経験を踏まえた包括的で参加型の仕組みが必要です。 健康づくりは「人びとに対して行う」ものではなく、「人びとと共に行う」ものです。UO-UC は、生徒、家族、教員との協働的な方法を用い、当事者の声がプログラムに反映されるよう努めています。
3.健康とは、人、社会、そして地球との“ つながり” の中にあるものです。
UO-UC が現在進めている「健康のためのソーシャル・デザイン」では、デザイン思考を活用し、都市の設計、学校運営、ケアの提供方法など、日常生活そのものの中に「健康的な選択が自然になる」仕組みを共に創出しています。
UO-UC は、アジアを中心に世界中の協働ネットワークを育んできました。学校保健分野では、「日本学校保健研究コンソーシアム」と連携し、中国、カンボジア、インドネシア、ラオス、ネパール、韓国、フィリピンなどの専門家と協働しています。
包括的性教育(CSE)、特に月経教育に関しては、国際シンポジウムを開催し、限られた資源環境でもこの重要な教育を担う教師たちの育成・支援について研究を重ねてきました。また、COVID-19パンデミック中の若者のメンタルヘルスのニーズについては、WHO神戸センターと連携し、さらに、医療におけるAI の倫理的活用については、オックスフォード大学との協働で、市民参加による方針づくりに取り組んでいます。
UO-UC は「グローバルヘルスと教育」の大学院プログラムを開始し、今後は「プラネタリーヘルス(地球の健康)」や「健康のためのソーシャル・デザイン」に関するオンライン講座を世界中の学習者に提供する準備を進めています。
SDGs の時代が終わろうとする今、次なるグローバル行動は「育むこと(Nurture)」を根幹に据えるべきです。人を、地域社会を、そして私たちを支える地球を育むことです。
それはつまり、以下の点を重視することです。
・子どもや若者が、安全で、大切にされ、支えられていると感じる環境を育むこと─単に生き延びるのではなく、健やかに花開くために。
・学習者が自らの健康を大切にし、他者の幸福に貢献する知識・技術・自信を身につけられる教育制度を育むこと。
・一律的な解決策ではなく、信頼と共創に基づいた、分野や国境を越えたパートナーシップを育むこと。
その上で、UO-UC は以下の行動を続けていきます。
● 学生、教員、保護者、地域住民などのステークホルダーと「共創」し、地域の実情と価値観に根ざした健康的な環境を構築します。
● 創造性と協働によって、健康的な生活をより直感的で実現しやすく、かつ公平にする「健康のためのソーシャル・デザイン」の理念を健康教育に組み込みます。
●「ヘルス・アセット」アプローチを通じて、人と地域社会がすでに持つ強みを見出し、活用します。
● 地球環境への配慮を忘れず、今の選択が将来の人類と自然の健康を育むものであるよう努めます。
この道のりは簡単ではありませんが、私たちにとって不可欠な歩みです。いのち会議は、さまざまな組織と連携して、教育者、研究者、学生、政策立案者、産業界、そして「より健康な未来は、より包摂的で、よりつながりがあり、より思いやりのあるものでなければならない」と信じるすべての人と共に歩んでいきます。
【参考情報】
・大阪大学ユネスコチェア公式サイト(日本語)
https://ou-unescochair-ghe.org
・大阪大学 大学院人間科学研究科 MeWプロジェクト
https://mew.hus.osaka-u.ac.jp/
・大阪大学 CMCセンター
https://cmc-osaka.com/
・大阪大学 AIDEプロジェクト
https://en.aide.osaka.jp/
【アクションパネル】
医療・福祉
【SDGs】