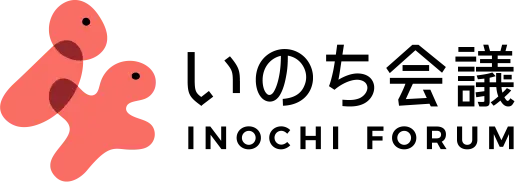いのち宣言
【提言】「庭」という自然と人を結ぶ空間を通じて「いのち」を共に感じ、考え、分断と不安の時代を乗り越えよう。
概要
私たちにとって「いのち」は、あまりに身近であるがゆえに、その本質を深く考える機会がほとんどありません。
しかし、身内の死に直面するなどの経験を通じて「いのち」には終わりがある事を知り、その中でどう生きるのかを問うようになります。
「いのち」が有限であることを前提に生きることは、人間だけが持つ感性であり、生を深く理解する出発点です。そしてその「いのち」は、決して個人だけのものではありません。植物や動物、微生物といった他の生命と同じように、私たちは自然循環の中にあり、互いに影響を与え合いながら存在しています。つまり、「いのち」は他者や自然との関係性の中で初めて成り立つものであり、日本文化における「巨石や道具にも魂が宿る」という感覚も、そうした価値観に根ざしています。
この「いのちの連鎖」と「関係性の中の自分」を再び実感するための試みが、株式会社梅鉢園の梅野星歩代表が推進するアート・文化活動「Commons Garden」です。 庭という囲われた空間を用い、人と自然、人と技術、人と人のつながりを「身体・感情・記憶」で体感できる場をつくるこの活動では、京都の庭師が受け継いできた伝統技術と、AIやデジタルを融合させ、「過去・現在・未来」が重なる時間と空間を演出しています。
なぜ「庭」が必要なのでしょうか。庭の共通点は、Garden、Park、Paradise、圓林、沙庭、斎庭など古今東西を問わず、「囲われている」ことです。囲われているということを通じては、庭は日常と非日常の境界をつくる役割を果たし、宗教儀式や祈り、鎮魂、祭事など形は違えど共感する場を人類に提供してきました。違う世界を接続させる中間領域という役割の庭は、生と死、自然と人との関係をも結ぶ場所でした。Commons Gardenもまた、そうした非日常の場を通じて、日常では見えなくなった「いのち」に再び触れる試みです。
活動の根底にあるのは、「いのちはコモンズである」という理念です。空気や水のように、「いのち」もすべての人が持ち、分かち合うべき共有資源です。奪い合えば枯渇し、育て合えば豊かになるもの。「文化=耕す」営みとして、いのちの土壌を耕し、対話し、実りを分かち合う文化の芽を育てていくことが重要です。
Commons Gardenは、2023年のG7広島サミットを皮切りに、世界遺産の醍醐寺や仁和寺などで展開されてきました。そこでは、答えを示すのではなく、風を感じ、他者と沈黙を共有しながら、自分だけの問いと向き合う体験が生まれました。それは、宗教でも哲学でも科学でもない、自らの「自灯明」に気づく場なのです。
Commons Gardenは、単なるアート活動ではありません。社会制度を変える前に、まず「感じる力」、「考える場」、「共感する関係性」を育てるための実践です。今後、この活動を全国、そして世界に広げ、都市や被災地、地域文化と連携し、「いのち」を見つめ直す場を増やしてくことが重要です。また、縦割りを超えて、教育・医療・福祉分野などの多様な人びとと連携し、いのちを共感し合えるエコシステムや社会が目指されるべきです。
いのち会議は、Commons Gardenの活動に参加することによって、いのちにとって本当に大切なものは何かを自ら問い直す人を増やし、分断と暴力の時代をみんなで乗り越えていきたいと考えます。
今この瞬間を、そして「いのち」をともに感じ、考え続けましょう。


参考情報
・G7出展 ‣ 株式会社梅鉢園
https://umebachien.jp/works/g7%e5%87%ba%e5%b1%95/
・EXPO2025に向けて世界文化遺産 京都 醍醐寺内イベント 第一回日本国際芸術祭に出展します ‣ 株式会社梅鉢園
https://umebachien.jp/news/日本国際芸術祭に庭園アートを出店します/
関連するアクションパネルのテーマ
11.アート・文化・スポーツ
関連する「いのち」
いのちを「かんじる」
関連するSDGs