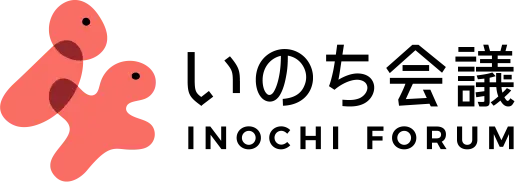いのち宣言
【提言】いのちへの共感やつながりを感じることができるエンターテインメントの空間を、移動可能・変形可能な構造をもつ施設の普及によって広めよう。
概要
私たちは今、社会のなかにエンターテインメントが自然に息づき、人々の感性や想像力が育まれる場の必要性を改めて見つめ直す時に来ています。
音楽や演劇、スポーツ、体験型アートなどを含む広義の「エンターテインメント」が行われる施設は、「いのち」や「共感」、「つながり」を、多様な人々が分かち合える空間です。現在の日本においては、このエンターテインメントを表現・共有できる施設が十分にあるとは言えず、またテクノロジーの進化や人びとの価値観の変化により、エンターテインメントの表現形態も急速に変わり続けている中で、施設を提供する側がそれを受け止めることができていない状況にあります。
そこで今、見つめ直すべき課題は、エンターテインメントを支える施設の構造の柔軟性です。資材不足や不安定な供給網などの問題も考慮に入れるならば、持続可能で多用途に活用できる構造で構成できる空間が必要です。
そこで重要となるのが、「Relocatable structure(移動可能な構造)」「Semi-permanent structure(準恒久的な構造)」「Adaptable structure(可変な構造)」という概念です。これらの構造は、従来の「一度建てたら形を変えず、同じ場所で数十年同じ用途で使用する」という施設とは異なり、再利用可能な部材を使いながら、設置・移動・拡張・縮小などが可能です。空間そのものを「変化に対応できる存在」として設計することで、より多くの人びとに、より多様な文化・芸術体験を提供できる基盤となります。国際博覧会や音楽フェスティバルをはじめとして、世界各地ではすでに、こうした構造を用いた施設の導入が始まっています。
ES Globalは、1974年からイギリスを拠点に、再利用を想定した鉄骨資材を活用したエンターテインメント向けの構造体を数多く提供してきました。世界中のミュージックステージや万博向けのパビリオン、オリンピックの会場などにおいて、この資材で組み立てた施設をレンタル形式で提供し、イベント終了後にはその資材を回収し、新たな場所、新たな形で再利用するという、環境にも配慮した循環型の運用を実践しています。ES Globalの構造体は、エンターテインメントに対応できる耐荷重とステージに必要なテクノロジーや放送等に対応できるよう設計されています。
日本においても、東京オリンピックの競技会場や大阪・関西万博の海外パビリオンなど、開催後に撤去が必要な仮設建築物と扱われる施設に対し、この再利用可能な資材を用いた施設を提供しており、実績を積み重ねています。現在日本国内では、建築資材の供給が逼迫しており、調達に時間を要するという深刻な課題に直面しています。今後の空間づくりを安定的に行うためには、この資材不足への対応が急務です。エンターテインメント施設では、設置や移動が柔軟にできる中期的な建築物(中期建築物)のニーズが高まっています。その実現には、日本と海外の建築資材の規格を互換させ、海外製の安全な資材を活用できるようにすることが重要です。これにより資材調達の選択肢が広がり、建設の遅れも防げます。制度整備や業界団体の設立を通じて、こうした動きを後押しすることが求められています。
ES Globalは、文化・芸術・エンターテインメントを通じて「いのちを感じる空間」を広げるため、柔軟で持続可能な建築構造の社会実装を進めていきます。2027年までに、中期建築物に関する業界団体を設立し、制度改正に向けた準備と提案を進めます。2026年から2035年は、海外部材の活用を可能にする制度整備を目指します。これにより、資材不足や建設費高騰への対応が可能となります。また、2030年頃までは、万博や文化イベントなどを活用し、実証実験を行いながら制度化に必要な実績とエビデンスを蓄積していきます。そして、2035年以降は、教育・福祉・防災・地域振興など多様な分野への展開を進め、いのちを感じ合える空間が社会に広がることを目指します。
いのち会議は、ES Globalなどと連携し、柔軟で再利用可能な空間構造の社会実装を推進することで、誰もがアートやエンターテインメントを通じていのちを感じ、慈しむ心を育める包摂的な社会の実現を目指します。また、万博をはじめとする文化イベントの場を活用し、制度改革の必要性を発信するとともに、行政・産業・市民をつなぐ対話の場づくりにも積極的に取り組んでまいります。


関連するアクションパネルのテーマ
9.資源循環
11.アート・文化・スポーツ
関連する「いのち」
いのちを「かんじる」
関連するSDGs