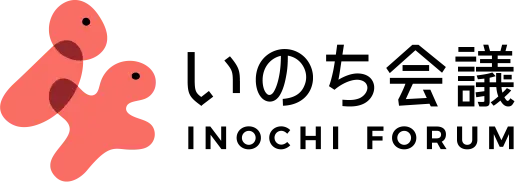いのち宣言
【提言】「歌の力」を信じ、歌が好きなすべてのこどもが自分の地域で定期的に歌を体験できる拠点を創り、一人でも多くのこどもが生きる力を身につけられるようにしよう。
概要
音楽は人びとが成長するうえで大きな影響を与えています。
音楽のなかでも特に「歌」には言葉があり、さまざまな歴史や文化、祈りや想いが込められています。また声を発し呼吸することで健康を維持することもできます。
全国どんな小さな市町村にも歌好きなこどもがたくさんいます。約50年前の全盛期とよばれる時代は、各市町村にも児童合唱団(少年少女合唱団)があり、多くは100名を超える大規模なものでした。しかし約30年前から少子高齢化が進み、受験社会のなか、学校以外のアフターを塾などに時間を費やすこどもが増え、全国の児童合唱団は衰退の一途をたどっています。追い打ちをかけるように、2020年の新型コロナウィルス感染症により、多くの児童合唱団がなくなり、かろうじて細々と一桁の人数で続けている団体が大半を占めるようになりました。
このような状況に対して、一般社団法人Art MICEは、「歌の力」を信じ、どんな小さな市町村でも歌好きのこどもが定期的かつ継続的に歌の体験ができる拠点の創造を目指しています。
大きな課題として、地域における歌の指導者の確保があります。毎年、多くの音楽大学から卒業生が社会に送り出されています。卒業生は、小さい頃から多くの時間を割いて音楽と向き合ってきた人たちです。しかしそのほとんどが音楽だけを生業としていないのが実情です。日本では、音楽が社会にとって不可欠なものと認められていないからではないでしょうか。
西洋では、芸術はいのちを高めるものとして扱われ、各地域で音楽学校があり、その学校がその地域での一番の進学校にもなっています。つまり音楽を小さい頃から定期的に体験することで、さまざまな能力が身につくことがわかっています。イギリスでは、医療分野で統合医療の一つとして「音楽」が用いられており、薬や手術だけでなく、音楽での療法が積極的に取り入れられています。
日本でも、各地域での児童合唱の取り組みを通じて、たくさんの優秀な生徒を世に送り出している指導者は少なくありません。現場では、「発達障がい」のこどもも多く参加しており、歌による療育も実践され、成果をあげています。そしてその経験により、障がいのある子どもたちが豊かに日々を生き生きと活動しています。
Art MICEは、現在、政府が取り組んでいる児童発達支援や放課後等デイサービスで「歌の療育」に取り組めないか模索しています。福祉教育では2024年度に大きな法改正があり、放課後などのデイサービスでも「5領域」(健康・生活、運動・感覚、認知・行動、言語・コミュニケーション、人間関係・社会性)に渡って社会で生きていくための取り組みが必要不可欠とされました。「歌の療育」は「5領域」を達成するのに必要な要素がすべてあります。今後は、この「歌の療育」を医療機関や専門的な研究者と協働し、しっかりとした効果を示すエビデンスを作っていくことが必要です。歌がこどもたちのための療育に効果があることが示されれば、全国の市町村にある福祉教育施設において、こどもたちの成長に貢献する場、そして音楽を学んだ人のやり甲斐と生業につながる場が創れるはずです。
音楽は世界の共通語です。またそのなかでも歌はどんな国でも取り組んでいる音楽文化です。いのち会議は、Art MICEの活動方針に賛同し、世界中のこどもたちが「歌の療育」によって生きる力を身につけ、一人ひとりが幸せに暮らせる社会を目指します。


参考情報
・和歌山児童合唱団:こどもコーラスにより国際交流を通じて世界平和を目指している
https://wajido.jimdofree.com/
・高野山国際こどもコーラスフェスティバル:弘法大師「空海」が開いた祈りの聖地・高野山で、国内外のこどもコーラスが集結し、歌声により世界へ向けて平和のメッセージを発信するイベント
https://koyasan-chorus-festival.jimdosite.com
※「5領域」とは「健康・生活」、「運動・感覚」、「認知・行動」、「言語・コミュニケーション」、「人間関係・社会性」のこと
関連するアクションパネルのテーマ
2.教育・こども
関連する「いのち」
いのちを「かんじる」
関連するSDGs